京都検定講習会 特別プログラム
~時代祭「室町行列」が生まれるまで~
日時:2008年3月30日
会場:ひと・まち交流館
講師:猪熊兼勝先生(京都橘大学教授)
山路興造先生(民俗芸能学会代表理事)
河上繁樹先生(関西学院大学教授)
京都三大祭の時代祭。その行列に「室町時代」がなかった理由から
明治28年、第4回内国勧業博覧会が京都で開催
そのモニュメントとして平安神宮が創建され、桓武天皇が祭神とされた
京都に都があった1100年を衣裳で再現するパレードが提案された
桓武天皇が祭神のため、
南北朝時代に天皇家(後醍醐天皇)と対立した足利氏の室町時代は設定されなかった
平成7年、パリ市長から「時代祭をパリで」の依頼により、300人が出向き実施
このとき、フランスの研究者から「足利氏の列がないのはおかしい」と指摘される
↓
平成17年、室町時代列を増やしてほしいとの多くの要望
↓
平成19年、室町時代列が新設される
室町時代列は「室町幕府執政列」=将軍列 と「室町洛中風俗列」=庶民列 からなる
将軍列
足利将軍は足利義尚像(地蔵院蔵)を、御供衆は細川澄元像(永青文庫蔵)を元に復元
庶民列
風流(ふりゅう)踊りを復元してます
室町後期以降、民衆が自ら囃して踊るようになった
中踊りと側踊り(がわおどり)。踊りの中心には大きな唐傘
太鼓打ちと太鼓受けは別で、衣裳は「北野天神祭礼絵巻」を参考
大唐傘は「豊国祭礼屏風」を参考
踊りや囃しは滋賀県草津市老杉神社に残る「さんやれ」を参考
私は時代祭を見たことがないのですが、「音のない祭り」だったそうです
そこに室町庶民列の音と動きが加わりました
その後、衣裳製作に関するお話があり、室町時代当時の染織事情も紹介されました
尚、側踊りは当時、思い思いの衣裳を着ていたと思われ、
バラバラの衣裳にしたかったが、予算の都合で数種類になったと話されました
当日見せていただいた 時代祭の衣裳
左から:御供衆、足利将軍、太鼓打ち、太鼓受、側踊り
側踊りは小袖を片袖にして着ています。当時このような着方が多くなったそうです
キラキラしてるのは金襴ではなく、摺泊(すりはく)という手法だそうです
摺泊:金箔を着物に貼り付ける
今回、室町時代行列を復元された先生方のお話を聞くなかで、
ひとつの衣裳、ひとつの踊りまで、ここまで時代考証がされてるのか!と正直驚きました
尚、時代祭の衣裳は「みやこめっせ」で順番に展示されてるそうです
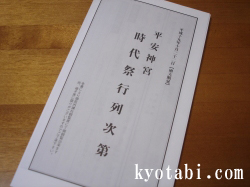 |
講習会でいただいた資料
観覧席で見る際にいただけるもの?
中には全ての行列が衣裳とともに書いてありました |
|

